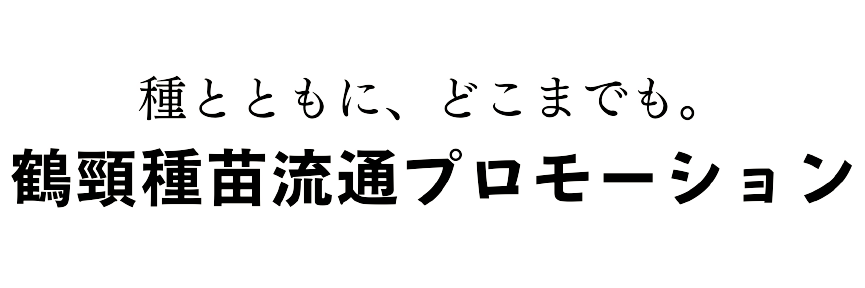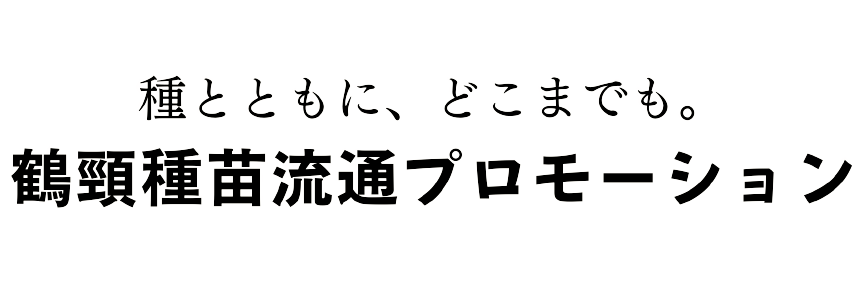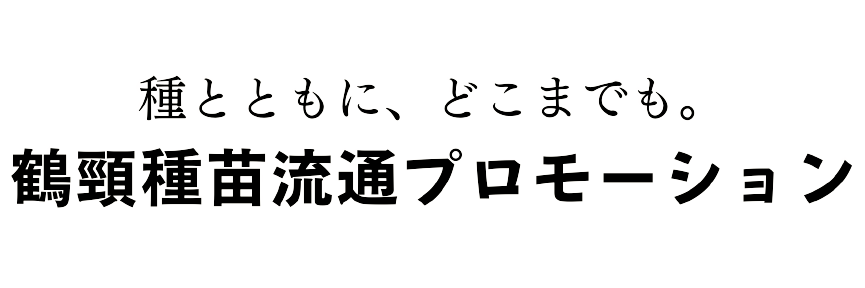2025/6/17 秋まき種子の販売を開始しました。今後、8月下旬まで順次入荷いたします。
-

六尺へちま(小袋:20粒)
¥297
一般的なヘチマに比べて果実が極めて長細く、しばしば1m以上になる。ヘチマ水の採取や束子としての利用のみならず、未熟果を食用にするのもよい。クセがなく、炒め物などに最適。 ーーーーー 採種地:岐阜県 発芽率:80%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

長野青皮越瓜(小袋:1ml)
¥297
長野県上水内郡古牧村高田附近(現・長野市)で盛んに栽培されたため「高田越瓜」の名前で親しまれた。新潟県上越市の「高田越瓜」とは異なり、これと紛らわしいため、本種は、全国的には「長野青皮越瓜」あるいは「長野越瓜」などと呼ばれている。 果形は長枕形の大型で、果重1kg程度で収穫する。果皮が濃緑色であることが特徴である。 ーーーーー 採種地:長野県 発芽率:85%以上(2025年11月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

ステラミニトマト(小袋:0.25ml)
¥297
SOLD OUT
1992年、京都のタカヤマシードが発表した固定種有支柱型ミニトマト。果実は赤色、糖度が8以上と高く、裂果しにくいのが特徴。 播種:2~6月→収穫:5~10月 ーーーーー 採種地:中国 発芽率:80%以上(2024年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

細工名縞瓜(小袋:20粒)
¥297
SOLD OUT
福島県河沼郡会津坂下町の細工名(さいくな)集落で栽培されてきたツケウリ。果皮が独特で、白~淡緑色の地に縦方向に濃緑色の模様が入る。似たような模様のツケウリには福井県在来の「かわず瓜」があるが、「かわず瓜」は果形がおおむね俵形であるのに対し、本種は中央下部がやや膨れ、首の部分が細長くなるものが多い。細工名集落に限らず、会津地方一帯には広く同様のウリがあったようである。 浅漬けや奈良漬けなどに最適。 本種は栽培期間中、農薬化学肥料除草剤不使用の畑で栽培・採種いたしました。 ーーーーー 採種地:福島県 発芽率:80%以上(2024年12月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

真渡瓜(小袋:20粒)
¥297
SOLD OUT
福島県北会津郡北会津村(現・会津若松市)で栽培されてきた緑色系のマクワウリ。果形は俵型、果皮は灰緑色で、銀白色の縦縞が入る。『福島県農業史』によれば北会津村では江戸時代から麦の間作としてマクワウリの栽培が盛んであり、本種は大正初期に平山常松によって導入、地域で選抜されて生じたそうである。 本種は栽培期間中、農薬化学肥料除草剤不使用の畑で栽培・採種いたしました。 ーーーーー 採種地:福島県 発芽率:80%以上(2024年12月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

島とうがらし(小袋:0.5ml)
¥297
沖縄県在来のトウガラシで、果長は2~3cm程度と小ぶり。果皮は熟すれば赤色になる。発芽適温は25~30℃、生育適温は25℃程度であり、沖縄県では通年栽培が可能。鷹の爪や八ツ房など広く栽培されているトウガラシとは異なる、キダチトウガラシというグループに属する。キダチトウガラシは世界中の熱帯や亜熱帯に広く分布しており、日本では沖縄県や小笠原諸島などで古くから栽培されてきた。沖縄では「コーレーグース」と呼ばれる(本種を泡盛に漬け込んだものも「コーレーグース」と呼ばれている)。 沖縄県では害虫であるナスミバエが発生しているため、島とうがらしをはじめトウガラシ類の青果の移動自粛が要請されている。生の島とうがらしは基本的に沖縄県内でしか食すことができないが、種子から自家栽培すれば沖縄以外でも食すことができる。 中間地:播種→3月中旬~6月下旬 収穫→6月中旬~10月上旬 ーーーーー 採種地:インド 発芽率:75%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

太長中辛とうがらし(小袋:0.5ml)
¥297
長野県松本市で栽培されてきた辛みの少ない、大型のトウガラシ。果長13〜15cm程度で、くさび型。大きくなるまで辛みは少なく(まったく辛くないわけではない)、万願寺唐辛子やシシトウのように青果として利用することができるという。 ーーーーー 採種地:長野県 発芽率:75%以上(2025年11月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

シュガーランプ(小袋:0.25ml)
¥297
SOLD OUT
果皮の赤いミニトマト。果実は直径3cm程度の正円形。「シュガーランプ」は"Sugar Lump"と書き、「砂糖の塊」の意だが、近年の高糖度トマトにはおよそ及ばない。また、裂果しやすいため栽培時には土壌水分の急激な変化や高温・低温には注意が必要。 ドイツ連邦中央部の小都市ハン・ミュンデン(Hann Münden)にあるErnst Benary Samenzucht社が1950年頃に育成したとされる。当初の名前は"Benary's Gartenfreude"であったが、アメリカ合衆国ウィスコンシン州ランドロフ(Landolph)のJ. W. Jung Seed社によって、1960年頃"Jung's Sugar Lump" として販売された。本邦では「シュガーランプ」という名称で1970年代初頭にはすでに導入されていたとみられる。 Benary社は歴史ある種苗メーカーであり、現在では花の育種で有名である。Benary社のサイト上では独語Gartenfreudeをほとんどそのまま英訳した"Gardener's Delight"の名称で掲載されている。 写真1・2枚目は埼玉県神川町の弊社圃場にて栽培したもの。2025年7月撮影。 ーーーーー 採種地:中国 発芽率:80%以上(2024年8月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

札幌大長南蛮(小袋:0.5ml)
¥297
SOLD OUT
明治期に岩手県南部地方から導入された大長のトウガラシ。弊社取り扱いの「南部大長南蛮」の北海道馴化種とみなして差支えないだろう。 果長10cm程度。一般的に「鷹の爪」や「八房」は上向きに実がつくが、本種は下向きに実がつく。辛みは強い。 ーーーーー 採種地:北海道 発芽率:75%以上(2024年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

八ツ房唐辛子(小袋:0.5ml)
¥297
熊沢三郎らによれば、日本のトウガラシは6品種群、17代表品種に分けられ、本種は、八房群の代表品種。八房群に近い品種群に鷹の爪群があるが、両者を比較すると、鷹の爪群は心立ち横繁性で長期にわたって成熟するため、手摘みに適し、果肉は薄く、乾燥容易であるのに対し、八房群は早生房成性で秋冷とともに一気に成熟し、果肉は厚いという特徴がある。従来は生育日数が短くなる中部、関東で八房群が好まれ、生育日数が比較的長くとれる四国、九州で鷹の爪が好まれたが、現在では両品種群とも本州全域で広く栽培されている。 ーーーーー 採種地:中国 発芽率:75%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

橘田中長茄子(小袋:0.25ml)
¥297
農林省園芸試験場久留米支場長を務めた秋谷良三によれば、本種は愛知県海辺郡甚目村上萱津の在来品種であり、「橘田」は育種に関わった橘田氏に由来するという。果形は中長、果皮は紫黒色で中生のナス。種子が少なく食べやすいのが特徴。 関東地方で盛んに栽培されていた真黒茄子に比べて耐病性が高く、本種と真黒茄子をかけ合わせた、一代交配・「橘真」がつくられた。橘真茄子は実用的な一代交配種としては早い時期に広まったが、1961年にタキイ種苗から同じく一代交配種の「千両」が発表されると、徐々にその姿を消した。 ーーーーー 採種地:徳島県 発芽率:75%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

極早生 富津黒皮南瓜(小袋:10粒)
¥297
菊座系と縮緬系の自然交雑によって生じたとされる黒皮のカボチャ。果皮に10条の溝が入る。 以前は東京や千葉県の松戸地域で栽培が盛んであったが、大正5-6年に千葉県富津町に産地が移り、今日では「富津黒皮南瓜」の名で呼ばれている。砂地での栽培にも適し、生育旺盛で極早生。肉質は日本カボチャらしく粘質。 ーーーーー 採種地:中国 発芽率:80%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:過酢酸 浸漬処理1回済(生産地処理) ※写真はイメージです
MORE -

黄金9号甜瓜(小袋:1ml)
¥297
マクワウリは色、果形、大きさなど外見さまざまであるが、一般的には果皮の色の違いよって、緑色系、白色系、黄色系の3つに大別される。日本におけるマクワウリの歴史は古く、縄文時代や弥生時代の遺跡からもその種子が発見されているとしばしば説明されるが、これは緑色系品種に限った話である。白色系及び黄色系の品種は明治期に日本に入ってきたとされる。白色系の甜瓜をしばしば「梨瓜」と呼び、黄色系のことをしばしば「黄金系」と呼ぶ。 本種は、千葉県農試の渡辺誠三氏によって、県内で普及していた千葉棗瓜より育成された黄金系品種。昭和6年に命名されたが、太平洋戦争中、原種の維持に苦難し品質が低下したため、戦後形質を維持しつつ極早生のものを再び選抜した。戦後、千葉県を中心に関東地方で普及した。砂地での栽培に適する。 果実は長卵形で小さく、果皮は鮮黄色で縦縞は入らない。早生で玉割れが少ないのが特徴。かつては、干潟メロン、九十九里メロン、千葉黄金などの別称でも呼ばれていた。 ーーーーー 採種地:徳島県 発芽率:85%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

奈良1号黄甜瓜(小袋:1ml)
¥297
マクワウリは色、果形、大きさなど外見さまざまであるが、一般的には果皮の色の違いよって、緑色系、白色系、黄色系の3つに大別される。日本におけるマクワウリの歴史は古く、縄文時代や弥生時代の遺跡からもその種子が発見されているとしばしば説明されるが、これは緑色系品種に限った話である。白色系及び黄色系の品種は明治期に日本に入ってきたとされる。白色系の甜瓜をしばしば「梨瓜」と呼び、黄色系のことをしばしば「黄金系」と呼ぶ。 本種は奈良県農試において在来の黄甜瓜より系統分離によって育成され、昭和11年に命名された黄金系品種である。黄金系品種は砂地栽培で糖度が高くなるとされているが、本種は湿潤な土壌への適応性が高く、大阪や奈良を中心に水田を利用して栽培が行われていた。 果形は長卵形で、大きさは中程度、果皮は鮮黄色で縦縞は入らない。中生で収量が多いのが特徴。ただし、貯蔵性は低い。黄金9号とともに東京、大阪等の大市場で広く流通していた。 写真1枚目は群馬県伊勢崎市の弊社圃場にて栽培したもの。2025年7月撮影。 ーーーーー 採種地:徳島県 発芽率:85%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

新大和2号西瓜(小袋:1ml)
¥297
奈良県を中心に広く栽培された大玉スイカ。果皮は濃緑色に縞があり、果肉は赤いという、今日わたしたちがイメージする最もスタンダードなスイカの外見である。 明治末期、既に渡来していた黒皮種と新たに海外から導入した「アイスクリーム」が自然交配、その中から優良系統の選抜が進められた。選抜の結果、大正15年、奈良県農試において「大和二号」「大和三号」「大和四号」が命名された。昭和4年、「大和三号」に「甘露」を掛け合わせた一代交配種「新大和」が誕生した。その後、「新大和」を固定化した「新大和一号」が登場した。「新大和」が人気を博し、雑種後代二代目、三代目などから生産したスイカが「新大和」や「新大和一号」として流通するようになり、この事態に対処するため、これらのスイカの総称として「新大和二号」が与えられた。「新大和二号」はその後、選抜が続けられ、一品種として確立した。 現在では、当初存在していた「新大和」や「新大和一号」ではなく、「新大和二号」が最もポピュラーとなっている。 ーーーーー 採種地:タイ 発芽率:80%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

おちうり(小袋:1ml)
¥297
愛知県尾張地方で栽培されてきたマクワウリ。果皮は灰緑色で、銀白色の縦縞が入る。現在、マクワウリと言えば果皮の黄色い品種が主流となっているが、黄金系の品種は明治期に導入されたものであり、緑色系の品種の方が日本においては歴史がある。 「まくわ」は岐阜県本巣郡真桑村に由来する。農林省園芸試験場久留米支場長を務めた秋谷良三は『まくわうり(園芸叢書7)』(1953年)において、マクワウリが応神天皇の時代に朝鮮半島から伝来したという俗説を紹介しつつ、マクワウリが徳川家光に献上され、その際に生産地に五位の位階を賜り、上真桑村に五位田という地名があることを紹介している。 本種は真桑村のマクワウリに比較的形質が似ており、黄金系とは異なる在来のマクワウリであると推察される。 果実は大形の長円型で、果重800g~1kgで収穫する。「おち」は蔓から果実が「落ち」たときが食べごろであることから。『あいちの伝統野菜』に認定されている。 ーーーーー 採種地:岐阜県 発芽率:85%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

かりもり(小袋:1ml)
¥297
尾張地方で古くから栽培されてきたシロウリ。明治以降、早生系の品種が分化され、現在に伝わっている。 果形は円筒形、果皮は濃緑色。果長20cm程度、果重900g程度になり、京都の桂瓜などに比べると小型である。揃いよく、多収で、主に奈良漬けや粕漬けなどの漬物に利用される。若採りしたものを浅漬けにするのもよい。 本種のようなウリ類を一般的にはシロウリ(越瓜)と呼ぶ。しばしば、シロウリを「白瓜」記すことがある。東日本のシロウリ(東京大越瓜、沼目、高田など)や京都の桂瓜は果皮が薄緑色であり、決して白くはないが、キュウリや本種に比べれば十分白い。本種は果皮が濃緑色であることから、「青瓜」と表記されることもある。 ーーーーー 採種地:中国 発芽率:85%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

大丸冬瓜(小袋:25粒)
¥297
近年、冬瓜と言えば、沖縄系の果皮が緑色で俵型のものが主流となりつつあるが、本種は、淡緑色で白い粉を吹いたような果皮をしており、果形は丸型。 耐暑性に優れ、生育旺盛で栽培容易。貯蔵性も高い。 ーーーーー 採種地:岐阜県 発芽率:70%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

愛知本長茄子(小袋:0.25ml)
¥297
昭和初期、尾張地方北部でナスの抑制栽培が始まり、その際に導入された品種の尾張地方馴化種。詳しい品種は不明。 耐暑性強く、栽培しやすい。一般的には果長25cm程度で収穫する。 「あいちの伝統野菜」に認定されている。 ーーーーー 採種地:中国 発芽率:80%以上(2025年8月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:ジベレリン種子浸漬1回済 ※写真はイメージです
MORE -

本鷹の爪唐辛子(小袋:0.5ml)
¥297
熊沢三郎らによれば、日本のトウガラシは6品種群、17代表品種に分けられ、本種は、鷹の爪群の代表品種のひとつである。 鷹の爪群に近い品種群に八房群があるが、両者を比較すると、鷹の爪群は心立ち横繁性で長期にわたって成熟するため、手摘みに適し、果肉は薄く、乾燥容易であるのに対し、八房群は早生房成性で秋冷とともに一気に成熟し、果肉は厚いという特徴がある。従来は生育日数が短くなる中部、関東で八房群が好まれ、生育日数が比較的長くとれる四国、九州で鷹の爪が好まれたが、現在では両品種群とも本州全域で広く栽培されている。 文献上では、鷹の爪群は節成り、八房群は房成りであるとされてきたが、松島憲一らによる近年の調査研究では、鷹の爪系品種はいずれも房成りと報告されている。 ーーーーー 採種地:中国 発芽率:75%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

会津早生菊南瓜(小袋:10粒)
¥297
SOLD OUT
会津地方に江戸時代から伝わる日本南瓜。 未熟果は暗緑色だが、成熟果では薄い赤褐色の表皮となり、縦に10条の溝ができる。果肉は橙紅色で粘質。 開花後40~50日で収穫可能。貯蔵性あり。放任栽培可能。 本種は栽培期間中、農薬化学肥料除草剤不使用の畑で栽培・採種いたしました。 ーーーーー 採種地:福島県 発芽率:75%以上(2024年12月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

南部大長南蛮(小袋:0.5ml)
¥297
SOLD OUT
岩手を代表する激辛大形ナンバン(=トウガラシ)。果長は鷹の爪よりも長く、10~12cm。着果数多く、豊産で、家庭菜園に最適。 青いうちは焼き唐辛子や天ぷら、油いために。熟したのちは、乾燥して調味料へ。 播種:3~6月→収穫:7~10月 ーーーーー 採種地:高知県 発芽率:85%以上(2025年1月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE -

和多田瓜(小袋:2ml)
¥297
SOLD OUT
佐賀県唐津市に伝わる野菜瓜。果皮は濃緑色で縦に浅い溝が入る。歯ごたえがあり、奈良漬けに最適。 (本種はインターネット直販限定品です。店頭販売はございません。) 和多田瓜について、この種子の生産者についてもっと知る↓(鶴頸種苗流通プロモーション公式HP) https://kakukei-seeds.amebaownd.com/pages/6725478/page_202301131051 ーーーーー 採種地:佐賀県 発芽率:75%以上(2024年11月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※本年発芽不良のため10%増量の2.2ml入りとなっています。 ※写真はイメージです
MORE -

大獅子ピーマン(小袋:0.5ml)
¥297
来歴、詳細は不明。果実は大きく丸形。 大正14年春季・瀧井彌右衛門商店のカタログに「大獅子蕃椒」の掲載あり。同一品種か。 写真1枚目は群馬県伊勢崎市の弊社圃場にて栽培したもの。2025年7月撮影。 ーーーーー 採種地:インド 発芽率:75%以上(2025年10月現在) 有効期限:発芽率検査月より1年 薬剤処理等:なし ※写真はイメージです
MORE